目次
⒈睡眠と自律神経

睡眠は、疲労回復を早め、 免疫力を向上させ、 自律神経のバランスを整え、さらには記憶の整理・定着にも欠かせません。
そして、人体の生命を保つほかの機能と同じく、自律神経によって調整されています。
昼は緊張をつかさどる「交感神経」に従って活発に動き、夜はリラックスをつかさどる「副交感神経」に従ってゆっくりと休み、昼間の疲れを癒します。
だから、そのスイッチの切り替えがうまくいかないと、夜になっても活動的な状態のままなので、眠る準備に進みません。
自律神経に刻み込まれた「緊張」とは、命の危機に直面している事態(と脳が判断している)を指します。
脳が想定する世界は、はるか昔の人類がむき出しの自然や他民族による命を失う脅威にさらされている世界です。
一触即発の危険に直面して「とにかくこの一瞬を生きのびて、命を先につながなければ」という反応が必要(と脳が判断している)な状況なのです。
今の日本の日常生活では通常不要な反応ですが、文明の進化にからだが追い付いていないので、「とりあえず命を守らねば」というせっぱつまった強い使命感が、いまだに根強く残っているのです。

からだがこういう状態のとき、交感神経の「妄想」の中ではリラックスすることはそのまま「死」につながります。
ですから休むべき状況になっても、全身が「逃げる」または「戦う」ために身構えた緊張状態のままになります。
血液は手足の先から呼び戻されて体の深いところに集まり、心臓の鼓動は早まり、食欲も封印されます。
その結果、手足の先は冷たく、頭は冴え、「眠る」ことなど問題外の「不眠の夜」に突入するのです。
こういう状態になってしまう原因の第一は、しばしば「ストレス」です。
それは、ストレスの渦中にあるときはからだの力をうまく抜けず、寝ても起きても首まわりがガチガチに緊張して「首こり」の状態になってしまうからです。
迷惑な指令ではありますが、命を守ることを第一とする交感神経の役割りからは必然なのです。
そして残念ながら、一定以上の緊張が続く限り「心地よく深い眠り」は訪れません。
ここで、鍼灸治療の優しい刺激が加わると、首の筋肉の緊張が減って首こりが改善し、脳の働き過ぎも必要なくなるので、交感神経優位からの緊張も解消されて、眠ることができるようになります。
長く鍼灸治療に通ってこられるかたの中には、治療後の深い眠りを楽しみにして通われる方が大勢いらっしゃいます。
⒉睡眠と体温

寒い季節、寝床があたたか過ぎても、冷たいのと同様、よく眠れないことをご存知ですか?
睡眠と体温は関係が深く、睡眠中は体の深いところの温度(深部体温)が、起きているときより1~2度低いので、眠りに入るときは、手足の末梢血管が広がって放熱し、深部体温を下げようとします。
そして、わたしたちが眠気を感じるのは、この体温が下がるときです。
うまく下がらないと寝つきが悪く、熟睡もできません。
赤ちゃんが眠いときは手足がポッポとあたたかくなります。
眠そうなのにむずかって眠らない時は、体温がスムーズに下がらず、眠いのに眠れないからです。
また、寝床の中の快適温度は四季を通じて33℃くらいといわれています。
寝床の中がこの温度を超えて温かすぎると、末梢からの放熱が妨げられて、深部体温がうまく下がりません。
すると時間が経っても、すぐにも仕事ができそうなくらい元気よく目が覚めたままになり、やっと眠れてもすぐ目が覚めてしまう、ということが起きます。
これは深部体温が下がらないため、からだの中の「on/off」のスイッチが切り替わらず、日中と同じ「on (交感神経優位)」のままだからです。
電気毛布などの上手な使い方として、寝床に入る前に十分あたためておいて、自分が横になるときに電源を切るのがよい、と言われます。
必要な水分を失わないためにも、あたため過ぎには注意しましょう。
⒊自分でできる睡眠の質改善
睡眠は、食事や運動と並ぶ健康維持の大きな柱です。
とくに暑さが厳しい期間は、エアコンで室内温度を調整しても寝苦しさは残ります。
そんな夜が続くと疲れがだんだん重なって、自律神経の調子も悪くなり、少し気温が下がる秋口に、一気に体調が崩れる、ということも起きかねません。
そこでまず、自力でできる睡眠の質改善の方法についてサラッと見てみましょう。
☆くわしい内容はコラムをご覧ください。
⑴寝返りが自由にできることが睡眠の質の決め手
あまり意識されない「寝返り」ですが、健康に大きくかかわってきます。
寝返りは、昼間の仕事による筋肉の疲れをリセットするだけでなく、血液・リンパ液・関節液の循環を促進して疲労回復や免疫向上に貢献します。
自由に寝返りが打てる環境でないと、熟睡もできず疲れも解消できないので、体をこわしてしまいます。
⑵良い寝具→スムーズに寝返りを打つために!
「寝返り」は、体の軸の背骨を中心に、右から左、左から右へと転がる行為です。
寝苦しくて、寝心地のいい場所や寝やすい姿勢を探して動くのとは違います。
①敷ふとん
敷ふとんで一番大切なのは、重たい腰が沈まないこと。
硬さの目安としては、畳の上に綿ふとん1枚くらいがよい、といわれます。
寝返りの打ちやすさも大事です。
仰向けに寝て両腕を胸の前でクロスし、両ひざを立てて左右に回転してみて、腰や肩に力が入らないか、肩と腰が同時に寝返りを打てているか、をチエックします。
寝返りの打ちやすさは枕の高さによっても変わるので、敷ふとんと枕は一緒に調整したほうがいいでしょう。
②枕

枕を選ぶ時の大事なポイントはふたつ。
*首の角度を正しく保てるか?
*スムーズな寝返りが打てか?
枕は肩口まで
日中の基本姿勢では、体幹が常に頭の重さや首を体幹が支えていなければなりません。
だからこそ、夜寝るときは昼の疲れがとれるように体に負担をかけない睡眠姿勢で、体幹や首の筋肉を休ませてあげることが大事です。
それには、自分の肩口まで枕を引き寄せて深めに頭を乗せるのが、理想的な当て方です。
枕がからだに合っていないと、朝起き抜けに、肩こり・頭痛・疲労感がある、などの不調を感じることがあります。
枕の大事な役目は、首の骨の緩やかなカーブを正しく保つことです。
枕が合っていないと首まわりの筋肉が緊張し、肩こりの原因となって、首筋や肩の後ろ、肩甲骨の周囲に痛みを感じるようになります。
また、頭痛には、姿勢や首にかかる負担による筋肉のこりが原因で発症する「頸性頭痛」があります。
頚性頭痛の特徴的な症状は「疲労感」ですから、枕が合わず首周りの筋肉が緊張しっぱなしであることが原因かもしれません。
③掛ふとん
ここでも、寝返りが楽に打てることがポイントになります。
重さ、素材、カバーに注目し、軽くて暖かい羽毛ふとんがベストと言えます。
④パジャマ
やはり、「寝返りが楽に打てるか」がポイント。
首まわりにフードが付いているもの、汗を吸うと重たくなる素材、モコモコしたフリースなどは寝返りの妨げになります。
パジャマの上衣のすそはズボンの中に入れて、動きやすい状態にととのえます。
寝返りがスムーズにできれば、自然と体温が保たれてあたたかく眠れます。
⒋寝落ちについて
⑴寝落ちはいけません
テレビを見ながら、あるいはスマホをいじりながら、本を読みながら、自分でもわからないうちに寝入ってしまうことがあります。
このような寝方を「寝落ち」と言うそうです。
もともとは、オンラインゲームやチャットのやり取りをしながら眠ってしまい、そのうちに接続が解除されてしまうことから生まれた言葉だそうです。
この「寝落ち」、実はからだによくありません。
質の高い睡眠を確保するには、眠る態勢をととのえ、「ここから先は眠る」と自律神経もちゃんと切り替われるように、きちんと区切りをつける必要があります。
寝落ちする生活が長く続くと、その延長線上に入眠障害など様々なかたちの「スイッチが切れない」ための不眠症が待ち構えています。
⑵寝落ちを誘う要因
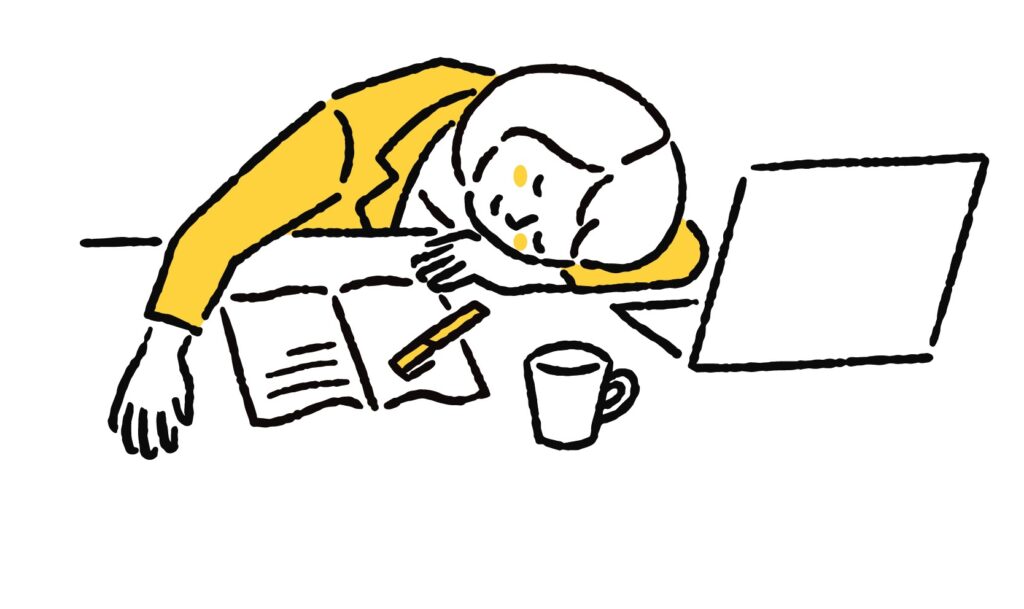
「寝落ち」を誘うファクターはいくつか挙げられますが、最大のものは睡眠不足です。
ひとは通常、睡眠時間が6時間を切ると眠気を感じます。
睡眠不足の上に、帰宅が遅い時刻になったり、夜の外での飲酒の後では、家に着いたとたんに安心し、疲労と気のゆるみから寝落ちしやすくなるでしょう。
もし「良質な睡眠」がとれていれば、もう少し眠気と戦えるはずです。
残念ながら「寝落ち」では良質な睡眠がとれません。
ぐっすり眠るには寝心地の良い寝床と、眠ってもいいんだ、という安心感が必要だからです。
寝具には、睡眠中の体温の確保と身体への負担が少ない姿勢を保つ、という2つの役割があります。
寝落ちしてベッド以外の場所で眠り、寝床に入るまでの数分間を節約してその分長く寝られたとしても、残念ながら疲労回復には役立ちません。
翌朝、爽快とはほど遠いこわばったからだで目が覚め、すっきりしない頭で1日頑張って、その結果さらに翌日も寝落ちする、という悪循環に陥る可能性も高くなります。
⑶寝落ちの悪影響
寝落ちが癖になると、他の生活習慣にも悪影響が及びます。
1.疲れ果てて帰宅すると、なんとか食事だけして即寝落ちしてしまう。
胃での消化活動のために、食べ物は3時間くらい滞留しています。
この夕食後3時間くらいは起きていないと、眠りが浅く睡眠の質が下がってしまいます。

2.入浴しなくなる
入浴には、深部体温を一時的に上げて心身をリラックスさせる副交感神経の働きを促進する作用があります。
眠りにつく1~2時間前に、あまり熱さを感じない程度のお湯につかると、睡眠の質が上がって大きな疲労回復効果が期待できます。
寝落ちすると入浴が省かれることが多いので、湯船につかるメリットを手放すというもったいないことになります。
3.自律神経のバランスが乱れやすくなる
寝落ちの悪習慣に染まってしまうと、⒈や⒉からわかるように、昼の活発に動く時間帯と、夜のゆっくり心身を休ませる時間帯とのしっかりした区分がつきにくくなり、自律神経のバランスが乱れてしまいます。
すると、疲れやすくて頭のはたらきもしっかりしない上に、肩こりや頭痛・耳鳴り・動悸・日中の眠気・胃腸の不調など、いろいろの症状が起きやすくなります。
⑷寝落ちをしないために
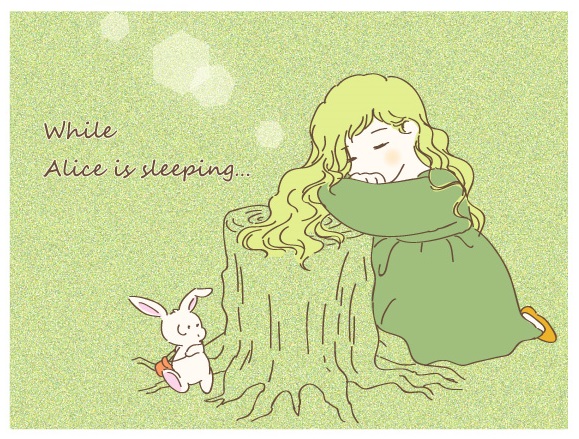
寝落ちを避けるには、とにかくそこまで疲れないこと、です。
1.短い昼寝をする
15時半には終わるような、短い(15~20分くらい)昼寝をしましょう。
それ以上遅い時間帯では、夜の睡眠に悪い影響がでます。
寝る前にくらべて頭がよくまわるようになることが科学的に明らかにされています。
また仮眠の前にコーヒーを飲んでおくと、目が覚めた時にちょうどカフェインの覚醒効果が出るのですっきりと活動できます。
2.毎日の睡眠の質を上げるよう心掛ける
食事は、就寝の3時間前にはすませ、シャワーだけで済まさずに必ず湯船につかることが大事です。
そして、眠る前には携帯電話をいじらないこと、軽いストレッチで昼間のコリをほぐすこと、などがおすすめです。
⑸病気の可能性

居眠り運転が度重なる場合は、専門の医師の診察を!
眠気がひどく日常生活に支障がある場合は、病気の可能性も考えなければなりません。
「睡眠時無呼吸症候群」や「ナルコレプシー」など、睡眠障害の治療を標榜する病医院での受診が必要な病気があります。
